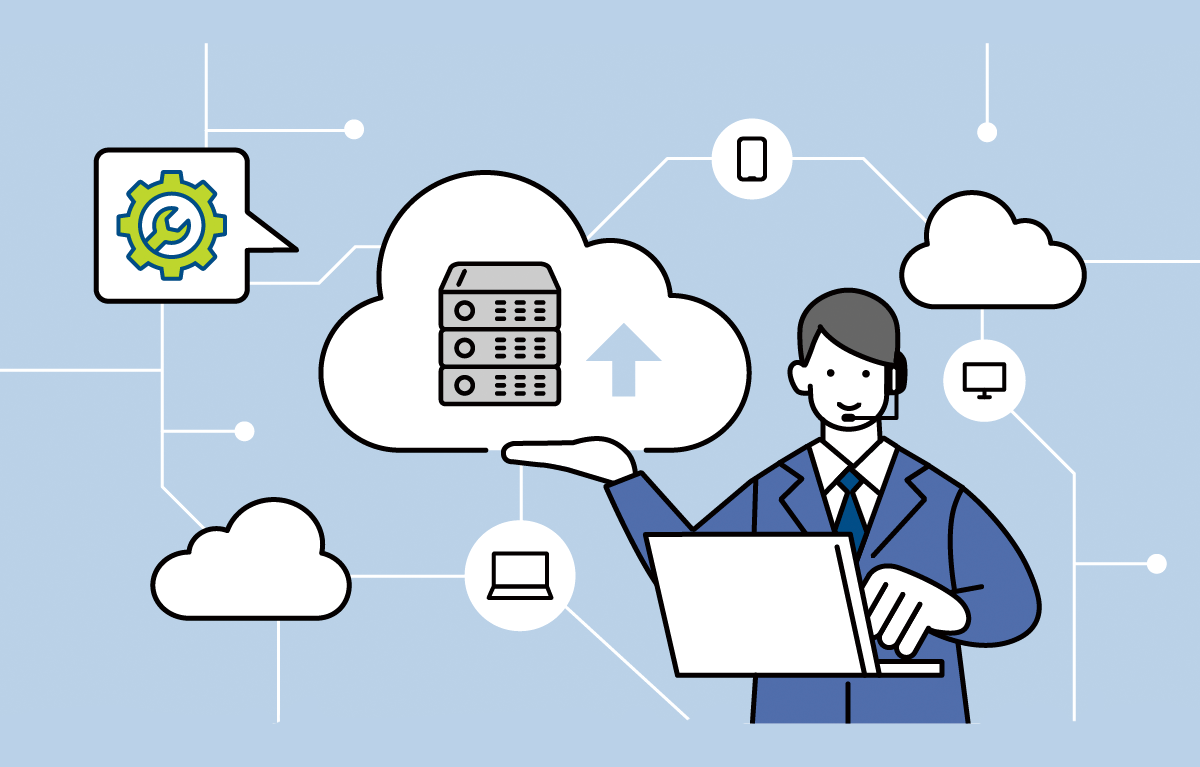企業がクラウドを導入する8つのメリット!注意点&検討ポイント
2023.01.04(水)
- クラウド

近年、リモートワークや在宅勤務などの働き方の多様化や、自然災害が起きた際の対策などで企業におけるクラウド活用が注目されており、年々利用する企業も増えています。
クラウドではさまざまなサービスが提供されているので、クラウドの導入を検討しているなら、その基本的な知識とサービスごとのメリットを把握するのが重要です。
本記事では、クラウドの基礎知識、利用するメリット、注意点、選び方のポイントなどを解説します。
クラウドとは?概要を解説
クラウド(クラウドコンピューティング)とは、インターネットなどを通じて、サーバーやネットワークなどのITインフラ、そのITインフラ上で稼働するソフトウェアや機能を、サービスとして提供する形態のことです。
ユーザーがITインフラやソフトウェアを持たなくても、必要なコンピューター資源や機能を、必要な分だけ利用することができます。
クラウドには複数の種類が存在しており、各サービスによって役割が異なります。まずは2つのポイントでクラウドの基礎知識を紹介します。
- クラウド環境の種類
- クラウドサービスの代表的な種類
それぞれ見ていきましょう。
クラウド環境の種類
クラウド環境は実装モデル(クラウドの利用機会の開かれ方)によって種類が異なり、以下の3種類が存在します。
種類 |
内容 |
プライベートクラウド |
自社専用のクラウド環境のことです。企業が自社内にクラウド環境を構築し、社内の各部署やグループ会社にサービスを提供します。自社で環境の構築・運用を行う「オンプレミス型」、クラウド事業者からサービスを受ける「ホスティング型」が存在します。 |
パブリッククラウド |
「AWS(Amazon Web Services)」や「Microsoft Azure」のようにクラウドベンダーが提供する環境を他の利用者と共同で利用することです。使いたいサービスを選択し利用できるため、使用した分のみ料金が発生します。 |
ハイブリッドクラウド |
「オンプレミスとクラウド」「プライベートクラウドとパブリッククラウド」など、要望に応じて組み合わせて利用することです。機密性が高いデータはプライベートクラウドに保管し、外部に公開してもよいデータはパブリッククラウドを利用するなど、自社の用途によって使い分けが可能です。 |
それぞれの環境によって役割や用途、導入方法などが異なってきます。自社の要望を明確にした上でクラウドを導入するのが好ましいです。
クラウドサービスの代表的な種類
クラウド環境の他に、提供されるサービスにもさまざまな種類が存在します。
種類 |
内容 |
IaaS |
サーバーやネットワーク機器などのハードウェアリソースをネットワーク経由で提供するサービスです。自社でインフラ機器を用意する必要がないため、物理的な調達・設置・保守の手間を省くことができます。 |
PaaS |
アプリケーションを構築・稼働させるための基本的な環境をネットワーク経由で提供するサービスです。ハードウェアやOSに加えてアプリケーションのベースとなる各種ミドルウェアまであらかじめセットアップされており、環境構築の手間を省くことができます。 |
SaaS |
完成されたアプリケーションや機能そのものをネットワーク経由で提供するサービスです。Webブラウザだけで利用できるサービスのほか、PCにソフトウェアをインストールして利用する形態のサービスもあります。 |
クラウドサービスは、企業のニーズに合わせて最適なものを組み合わせて利用可能です。導入前にクラウドを利用する目的を明確にしておくと、必要なサービスを選択しやすいでしょう。
次の章で各サービスのメリットをさらに解説します。
クラウドを導入する8つのメリット

laaSのメリット
まずは、IaaSを利用するメリットを紹介していきます。
キャパシティを柔軟に拡張・縮小できる
コンピューター資源をサービスとして利用できるIaaSでは、利用用途や状況に応じてそのキャパシティ(能力や容量)を柔軟に拡張・縮小して使うことができます。
利用シーンに合わせてサーバーやストレージ、ネットワークなどを必要な分だけ使用可能で、数クリック・数分でサーバーの作成・リソースの変更ができるサービスもあります。
新規事業を行う際にサーバー1台から始め、事業が軌道に乗ってきたら2台、3台と容易に増やせます。
また、事業の繁忙期に合わせてサーバー台数を増やし、業務が落ち着いてきたら台数を減らすといった活用も可能です。
オンプレミスでインフラ基盤を用意すると、機器の調達や構築に時間がかかり、一旦用意したキャパシティを柔軟に変更することもできません。万が一縮小する場合は、機器調達に要したコストが無駄になってしまいます。
IaaSを利用すると、自社の業務に合わせた最適なインフラ環境を、素早く入手でき、フレキシブルに活用できます。
思い通りの環境を構築できる
IaaSはサーバーやストレージといったインフラ基盤の提供のみ行われるため、基盤上に搭載するOSやミドルウェア、アプリケーションなどはユーザーが自由に構成することができます。
例えば、既存で利用している環境やアプリケーションをオンプレミスからクラウドに移転する場合でも、IaaSを利用すれば、その構成やプログラムを大きく変えることなく、スムーズに移行・展開することが可能です。
初期投資を抑えられる
IaaSを利用する大きなメリットとして、初期投資が抑えられることもあげられます。繰り返しになりますが、クラウドはサーバーやネットワークといったインフラ機器を自社で用意する必要がありません。
インフラ基盤を用意せず、必要なリソースを必要なだけ利用できるため、初期投資の負担やリスクを負う必要がなく、使いたい時に使いたい分だけ、迅速に利用を開始することが可能です。
参考に、自社でインフラ環境を整える際は、小規模環境でも20万~30万程度かかります。大規模なシステム開発となると、インフラ構築のみで数億円になることもあります。
PaaSのメリット
続いて、PaaSのメリットをチェックしましょう。
容易に開発環境を構築できる
PaaSは容易に開発環境を構築できるのが特徴です。
インフラ機器に加えて、OSや各種ミドルウェアを含むプラットフォーム一式が提供されるためです。
環境構築に要する時間や労力を軽減できるので、スピーディにアプリケーションの開発に取り掛かることができ、結果的にリリースを早めることが可能になります。
運用・保守を任せられる
PaaSで提供されている環境は、クラウド事業者が運用・保守を行っています。
具体的には、ハードウェアのトラブル対応、OSやミドルウェアのセキュリティ対策、バージョンアップ作業などです。
PaaSを利用していれば、こういった基盤側の運用・保守対応に煩わされることなく、アプリケーションの開発や保守に集中することができるでしょう。
SaaSのメリット
最後に、SaaSを利用するメリットを紹介します。
ソフトウェアの開発が必要ない
SaaSではネットワークを介してアプリケーションが提供されます。
ユーザーは利用したいアプリケーションを即時に利用することができるため、極めて手軽に導入が可能です。
例えば、SaaSの代表例としてビジネスチャットの「Slack」が挙げられます。
「Slack」ではチャットやビデオミーティングなどの機能が提供され、PCにソフトウェアをインストールして利用することはもちろん、ソフトウェアをインストールせずにブラウザから利用することも可能です。
料金プランも複数あり、一部機能に制限があるものの、無料で使うこともできます。
このように、SaaSはアプリケーションの開発を自社で行わなくても、必要な機能をすぐにサービスとして利用できるという魅力があります。
運用の負担を軽減できる
SaaSはユーザー側がシステムやアプリケーションを運用する負担を軽減できます。
これは、SaaSの提供企業が運用・保守を行っているためです。
例えば、自社でアプリケーションを開発している場合、当然その運用・保守も自社で行う必要があります。専門スキルが必要なので、IT担当者に依存することになり負担が増加しやすくなりがち。
SaaSを利用してアプリケーションの運用負担を軽減できると、今まで運用・保守に費やしていたリソースを他の業務に活用できるでしょう。
常に最新のアプリケーションを利用できる
ユーザーは常に最新状態のアプリケーションを利用できます。SaaSは提供企業が運用・保守に対応しており、定期的にアプリケーションのアップデートを行っているためです。
アップデートは、新機能の追加やセキュリティの更新などが行われます。ユーザー側は特に意識する必要がありません。
クラウドを導入する6つの注意点

クラウドの種類ごとにメリットを紹介しましたが、注意点(デメリット)もあります。それぞれの注意点を見ていきましょう。
IaaSの注意点
まずは、IaaSを利用する際に気を付けたいポイントです。
専門知識が必要になる
IaaSのコンピューター資源はクラウド事業者が用意したものを利用しますが、 ミドルウェアやアプリケーションなどの選定・導入は自社で行わなければなりません。
このことから、IaaSの利用にはITに関する専門知識が必要になっています。
クラウド事業者の中には、IaaSによる環境構築のサポートに対応しているケースもあります。専門知識に自信がない場合は、サポートが充実しているクラウドサービスを選ぶのがおすすめです。
また、国内にはクラウド活用を支援するパートナー企業も存在しています。クラウドの設計から構築、運用まで任せられるため、各クラウドサービスが認定するパートナー企業への相談も1つの方法です。
運用の負荷がかかる
IaaSではハードウェアの運用・保守を行う必要はありませんが、ミドルウェアやアプリケーションの運用・保守については自社で行う必要があります。
具体例を挙げると、以下のような運用管理が挙げられます。
- ユーザー登録の管理
- 認証・アクセス権限の管理
- 各種ログ・証跡管理
- ソフトウェアのバージョン管理
- 脆弱性対応、セキュリティ対策
- データのバックアップ
IaaSでは自社で運用する範囲が広くなるほど、担当者の負荷が増加します。
自社で運用するのが難しいなら、各クラウドサービスのパートナー企業に委託すると、運用・保守を任せられます。
PaaSの注意点
次に、PaaSについて、デメリットとなる可能性のある点をチェックしましょう。
提供元によりセキュリティ対策が異なる
PaaSに限らず、IaaSやSaaSでも同様ではありますが、セキュリティに対する方針や対策がクラウドの提供元によって異なります。
クラウドを利用する場合は提供事業者がどのようなセキュリティ対策を行なっているかをチェックし、信頼のおけるサービスであることを確認した上で利用しましょう。
また、PaaSではOSやミドルウェアの運用・保守・セキュリティ対策はクラウド事業者が行いますが、アクセス権限の管理やデータの保護、アプリケーションのセキュリティ対策などは自社で行う必要があります。
自社での対応に不安がある場合は、各クラウド事業者のパートナー企業に相談を。お客様の環境に適したセキュリティの提案やサポートをしてくれます。
システムの自由度が低い
PaaSはクラウド事業者が用意したプラットフォーム(ミドルウェアの構成や設定、対応するプログラミング言語など)を利用することになります。基本的な仕様が決まっているため、手間がかからず利用できる反面、システムの自由度が低いとも言えます。
より自由で柔軟な環境を求める場合には、IaaSの利用が適しているでしょう。
SaaSの注意点
さらに、SaaSの導入時に注意したい点を紹介します。
アプリケーションのカスタマイズ性が低い
SaaSで提供されるアプリケーションは、一般的にカスタマイズ性が高くないケースが多いと言えます。
すでに完成されたアプリケーションを利用するため、提供元企業が定めた範囲の中でしか利用を行うことができないのです。
SaaSサービスによっては、利用できるアプリケーションの組み合わせをカスタマイズできるケースもありますが、
基本的には、機能の追加や修正などはユーザー側ではできません。提供元企業による機能改善を待つことになります。
機能改善を待てない場合は、各クラウドサービスのパートナー企業に相談すると、自社の希望に応じた活用方法のサポートを行ってもらえる場合があります。
データ移行が難しい
現在利用しているサービスを他社のサービスに乗り換える場合、データ移行が難しいケースがあります。
クラウド事業者の指定範囲でしか利用できず、他のサービスとの互換性がない可能性があるからです。
クラウド事業者から「データ移行ができない」と言われた場合、新サービスでデータを1から蓄積しなおさなければなりません。
データの移行ができない場合、サービスの乗り換えに時間や手間がかかってしまいます。
そういったケースを想定して、利用を開始する際に、サービスの利用範囲をあらかじめ確認しておきましょう。
また、各クラウドサービスのパートナー企業に相談するとデータ移行をサポートしてもらえるため、自社で作業する負担を軽減することも可能です。
クラウドとオンプレミスの比較表
ここまで、クラウドのメリット・注意点(デメリット)を紹介しました。続いて、オンプレミスとの比較をしていきます。
オンプレとクラウド、それぞれの違いを把握することで、自社に向いているものを選びやすくなります。
クラウド |
オンプレミス |
|
コスト |
◯ |
× |
インフラ準備期間 |
◯ |
△ |
カスタマイズ |
△ |
◯ |
セキュリティ |
△ |
◯ |
既存システムとの連携 |
△ |
◯ |
障害対応 |
△ |
× |
バックアップ |
◯ |
× |
クラウドとオンプレミスの違いを把握し、自社に合うものを導入しましょう。
クラウドの利用が適した企業・検討が必要な企業

クラウドの導入には多くのメリットがあります。そのメリットが自社でどれだけ発揮されるかは気になるところです。
ここからは、クラウドの利用が適した企業・検討が必要な企業の特徴をまとめます。
クラウドの利用が適した企業
クラウドの利用が適した企業の特徴を解説します。1つでも当てはまる場合は、積極的にクラウド化を検討したいところです。
- コストを抑えたい企業
- キャパシティを柔軟に拡張・縮小したい企業
- 利用するキャパシティが決まっていない企業
- リモートワークを導入したい企業
「初期投資を抑えられる」「拡張性・柔軟性が高い」といったクラウドのメリットを取り入れたい企業は前向きに検討を。
また、クラウドは、ネットワークに接続できる環境であれば場所を問わず利用できることから、リモートワーク導入の際にクラウド化が進められるケースもあります。
クラウドの利用に検討が必要な企業
クラウドを利用する際に、検討が必要な企業の特徴を見てみましょう。
- 自由なカスタマイズをしたい企業
- 機密性が高い情報がある企業
- 自社システムとの連携がしたい企業
「自由なカスタマイズ」「機密情報の管理」「自社システムとの連携」などが気になる企業は、
クラウド活用のメリットを自社に合った形で取り入れるために、その方法を検討したほうがよいでしょう。
例えば、パブリッククラウドだけを利用するのではなく、プライベートクラウドやオンプレミス環境で自社サーバーを構築することも並行して活用することで、「カスタマイズ性」「機密性」「自社システム連携」が可能になります。
オンプレミス環境とクラウドを併用する「ハイブリットクラウド」は、双方のメリットを生かした構成にすることが可能です。
失敗しない!企業がクラウドを導入する時の検討ポイント

クラウドを導入する際のポイントを押さえていると、導入時に失敗することもなく、より効果的な活用ができるようになります。
企業がクラウドを導入する際に検討すべきポイントは以下にまとめます。
- 導入の目的を明確にする
- ランニングコストを計算しておく
- 運用体制を整える
それぞれチェックして活用してみましょう。
導入の目的を明確にする
クラウドの導入を成功させるには、目的を明確にするのが重要です。
企業がクラウドを導入するのは、あくまでも自社の課題を解決するための手段です。
目的を明確にすることで、企業が抱える課題の解決に最適なクラウドを選択可能です。
リモートワークを推進したい場合、ビジネスチャットツールやクラウドミーティングツールなどのクラウドシステムの導入が適しています。
ITインフラやシステム環境をカスタマイズしながら使うなら、「AWS」や「Azure」などのサービスが適しています。
クラウドを導入する際は、目的を明確にしたうえで適切なサービスを検討しましょう。
ランニングコストを計算しておく
クラウドを利用する場合、従量課金制になる場合が多くなります。従量課金制は、使った分だけ料金が請求されるスタイルです。
あらかじめランニングコストを計算することで、毎月の支出を把握しておくとよいでしょう。
ランニングコストを把握していないと、思わぬ料金が発生して驚くことになりかねません。
毎月のランニングコストを計算し、支出を見直すことでコストの削減につながります。
運用体制を整える
クラウドに限りませんが、ITインフラやシステムなどを導入する際は、運用体制を整えるのも重要です。
クラウドサービス側から提供される環境にはセキュリティ対策が行われていますが、
多くの場合クラウドベンダーが定める「責任共有モデル」の示す担当範囲に基づき、利用する企業側でもセキュリティ対策を行う必要があります。
自社で対策する範囲をしっかり把握し、事前に運用体制を整えることでセキュリティリスクに備え、万が一の際の損害を最小限に抑えられるようにしましょう。
また、いざというときのために、障害発生時の連絡先や対応フローなどをマニュアル化しておくと、慌てずアクションしやすくなります。
このようなセキュリティ対策や障害対応などの運用を自社で対応しきれないという場合は、クラウドの運用管理をクラウドベンダーのサポート企業に相談するのもよいでしょう。
導入するクラウドサービスの選び方
クラウドサービスを選ぶ際には、以下の4つがポイントになるので押さえておきましょう。
- コスト
- セキュリティ
- サポート体制
- 機能
1つひとつ見ていきましょう。
コスト
クラウドサービスの利用料は、従量課金の場合が多いですが、事業者によっては料金体系が異なることもあります。
複数のクラウドの料金体系を比較し、自社の利用状況でシミュレーションすることで、よりコストを抑えられるクラウドサービスを見つけられます。
ただし、料金の安さだけで判断すると、利用したい機能が使えないといったことになることも。
不足していた機能を利用するために他のクラウドに乗り換えるなどすると、結果的にトータルコストが高くなる可能性があります。
料金だけでなく提供されるサービス内容も確認して、自社の課題を本質的に解決できるクラウドサービスを選びましょう。
セキュリティ
先ほども述べた通り、クラウドサービスを利用する際は、提供元のセキュリティ対策のレベルや「責任共有モデル」の確認が必要です。
クラウドを利用する場合、自社のデータをインターネット上に保管することになります。セキュリティ対策が不十分だと自社の大切なデータがセキュリティリスクにさらされる可能性が高まります。
安心してクラウド活用をするために、セキュリティ面はしっかり確認しておきましょう。
サポート体制
クラウドサービスによってサポートの内容・体制が異なるので、事前にチェックしておきたいポイントになります。
サポート体制が充実していると、ITに詳しくなくても安心して利用できたり、万が一障害が起きてもスムーズに解決に導けたりします。
クラウドサービスのサポート体制を確認する場合は、下記の項目を確認しましょう。
- 導入時の相談ができるか
- システム構築を依頼できるか
- 問い合わせ方法、受付時間、回答時間、対応時間
- リモート作業、現地作業が可能か
サポートの充実度からクラウドを選ぶと、料金も高くなる可能性があります。自社で必要なサポートを明確にしてから検討しましょう。
クラウド移行・環境構築から運用、セキュリティ対策、請求代行まで、よりきめ細やかで一貫したサポートを受けたい場合は、各クラウドサービス事業者が認定するサポート企業に相談するのがおすすめです。
クラウドのメリットを把握しよう~まとめ~
DX推進が叫ばれる昨今、クラウドを導入する企業は増えてきました。
クラウドには、初期投資を抑えてスピーディーに導入できたり、必要に応じて機能を拡張できたりするほか、利便性が向上し業務効率が上がるなど、さまざまなメリットがあります。
しかし、クラウドにはメリットばかりでなく、注意点も存在しています。メリット・注意点の双方を把握し、自社に最適なクラウド活用の方法を探すことをおすすめします。
<クラウドの活用を検討している企業のみなさまへ>
さまざまなメリットを持つクラウドですが、導入のタイミングや進め方にお悩みを抱えていませんか?
また、自社のシステム運用に最適な環境をお探しではありませんか?
20年以上サーバーの運用に携わり、かつ、データセンターも保有し、さらに、
クラウドサービスプラットホーム最大手のAWSの認定資格を有する技術者が30名以上在籍する当社が、
御社に最適なITシステム環境をご提案します。