ファイアウォールのセキュリティ強化のポイントとは?具体的な設定方法と運用の効率化について詳しく解説
2025.03.03(月)
- 運用・セキュリティ

昨今、サイバー攻撃が高度化する中、ファイアウォールは外部の脅威からネットワークを保護し、組織の機密情報を守るために重要な役割を果たしています。
しかし、その効果を最大限に引き出すには、適切な設定と継続的な運用管理が不可欠です。
不適切な設定や運用管理はセキュリティホールを生み、重大なリスクを引き起こすおそれがあります。
本記事ではファイアウォールの設定ミスや不適切な運用が引き起こすセキュリティリスクに注目し、強化に必要なアクセス制御、監視、コンプライアンス対応の3つの要素を詳しく解説します。
また、基本設定から運用方法まで企業のセキュリティ対策に役立つ具体的な情報を提供します。
ファイアウォールのセキュリティリスク
ファイアウォールは、組織のセキュリティ対策の基盤として重要な役割を果たしますが、設定や運用が適切でない場合、大きなセキュリティリスクを伴います。
企業を取り巻くセキュリティの現状
自宅からのテレワークが広まる中、リモートアクセスの際の認証不足や不審なトラフィックの監視不足が問題視されています。
総務省の「テレワークセキュリティガイドライン」でも、ファイアウォールを有効にして適切な設定を行うことが推奨されており、ファイアウォールの重要性がますます高まっています。
また、国内における不正アクセス被害件数は年々増加傾向で、警察庁の調査によると、2023年には6,312件に上り、前年の4,112件と比べて約186.9%増加しています。
ファイアウォールの適切な設定と運用管理は、組織のセキュリティ対策において、極めて重要な位置を占めています。
不適切な設定や運用管理によるセキュリティ脅威
ファイアウォールの設定や運用管理が適切ではない場合、かえってセキュリティリスクを高める結果となりかねません。
主な脅威として、以下のようなものが挙げられます。
- 不要なポートの開放や誤ったアクセス制御設定により、外部からの不正アクセスが発生する
- 内部からの情報漏えいを防ぐための対応が不十分な場合、組織の機密情報が流出してしまう
- アプリケーション制御の設定が不十分だと、マルウェアの侵入を阻止できず、システムの乗っ取りや重要データの暗号化などが発生する
- 監視不足により、ランサムウェアなどの兆候が発見できず、攻撃に対する初期対応が遅れる
- ログ管理不足により、インシデントの原因を追跡できず、再発防止策が取れない
- ファームウェアやソフトウェアの更新不足により脆弱性が放置され、DDoS攻撃に悪用される
ファイアウォールの不備により発生した被害事例
サイバー攻撃による被害額は数十億から数百億円規模に達し、企業の信用や業務継続に深刻な影響を及ぼす場合もあります。
ここでは、ファイアウォールの不備が原因で実際に発生したサイバー攻撃の被害事例を紹介します。
事例 |
発生年 |
原因 |
主な被害内容 |
推定被害額 |
国立大学機構 |
2022年 |
ファイアウォールの設定変更時のミス |
約40,000件の個人情報が流出 |
復旧作業などで数千万円以上 |
米国の重要インフラ企業 |
2020年 |
ファイアウォールのゼロデイ脆弱性を狙った攻撃 |
20,000台以上のファイアウォールがマルウェアに感染 |
不明 |
効果的なファイアウォールのセキュリティ強化に必要な3つの要素

ファイアウォールのセキュリティ強化のためには、アクセス制御、セキュリティ監視、コンプライアンス対応の3つの要素に着目した運用が不可欠です。
適切なアクセス制御
社内ネットワークやシステムへ外部から不正アクセスするリスクや内部からの情報漏洩を防ぐために実施します。
最小権限の原則を徹底
アクセス権限は、ユーザーやデバイスに対して最低限必要な権限のみを付与し、過剰なアクセス権を与えないようにしましょう。
たとえば、特定の部署や役職に応じた権限設定を実施し、不要なアクセスを許可しないよう設定します。
許可・拒否ルールの明確化
アクセス制御では、ネットワーク内外の通信を管理するため、許可・拒否ルールの適切な設定が求められます。
ルール設定の際は、通信先アドレス、ポート番号、通信プロトコルを明確に指定しましょう。
また、トラフィックの双方向性(インバウンド/アウトバウンド)の管理も考慮し、必要な方向だけを許可して、セキュリティを強化します。
重複・未使用ルールの定期的な見直し
アクセス制御の設定後は、ルールの重複や未使用のルールがセキュリティリスクやパフォーマンス低下を引き起こすおそれがあるため、定期的な見直しが推奨されます。
最新のネットワーク構成に応じたルール管理をして、不要なルールは速やかに削除しましょう。
また、見直しは誤設定などに気づく機会にもなります。
セキュリティ監視と分析
ネットワーク内外で発生する異常や脅威を早期に検出し、被害が拡大するリスクを低減するためには、ログの監視と分析が必要です。
ログ監視
ファイアウォールのログは、ネットワーク内で発生する通信の記録として、潜在的な脅威の把握に役立ちます。
リアルタイムでのログ監視を行い、不正なアクセスや異常な動作の即時検知を行うことが望ましいです。
ログ分析の自動化と視覚化
ログ分析は複雑で手間がかかりますが、自動化や視覚化により、重要な脅威の迅速な検出が可能となります。
具体的にはフィルタリングでセキュリティ上の脅威となる可能性が低いリスクログを除外し、相関分析で異なるログデータの関連性を見つけることで、単独では見逃しがちな脅威の兆候を把握します。
さらにダッシュボードでの視覚化により、異常を即座に認識でき、容易に状況把握ができます。
効率的なログ分析に向けたSIEM導入
膨大なログの効率的な分析には、ツールの導入も不可欠です。
SIEM(Security Information and Event Management)は、ログの自動収集と一元管理やリアルタイムの異常検知、アラートとレポート機能により、監視の不足を補い初期対応の迅速化につなげます。
定期的なセキュリティリスク評価の実施
内部監査や第三者機関による評価を通じて、組織のセキュリティ管理体制を見直し、改善点を特定します。
単なる侵入テストにとどまらず、組織全体のセキュリティリスクを体系的に評価し、潜在的な脅威や脆弱性を明確化することで、セキュリティ管理の精度を高められます。
コンプライアンス対応
法令や業界の標準を遵守したファイアウォールの運用を行うことで、法的リスクや信頼損失を回避できます。
法令・業界標準の監査要件への準拠
企業は、法令や業界標準に基づく監査要件への準拠が求められます。
ファイアウォールの設定が特定の規制や基準(例:ISO、GDPR、PCI DSS)に適合しているかを定期的に確認し、遵守状況を記録する必要があります。
セキュリティポリシーの定期的な見直し
変化するビジネス環境に対応するため、セキュリティポリシーの内容を定期的に見直しましょう。
新たな脅威や運用ニーズに応じてポリシーを更新し、ファイアウォール設定もその都度、最適化していくことが求められます。
監査証跡の維持管理
情報セキュリティにおけるコンプライアンス対応の一環として、設定変更やイベントの履歴を管理する監査証跡の適切な保持が重要です。
監査証跡により、問題発生時に迅速な原因特定ができます。
ファイアウォールの具体的な設定方法

ファイアウォールの効果的な設定には、ポート制御やネットワークアドレス変換(NAT)、VPNの構築、IPS/IDSの設定といった複数の要素をバランスよく組み合わせる必要があります。
これらの設定は、セキュリティポリシーと連携しながら実施することで、総合的なセキュリティ強化が実現します。
本章では、ファイアウォールの基本的な設定からセキュリティポリシーの実装、監視・レポーティング設定までの具体的な手順を解説します。
ポート制御の設定手順
ポート制御は、外部からの不要なアクセスを遮断し、内部リソースへのアクセスを保護するためのもっとも基本的かつ重要な設定です。
システム管理者は、以下の手順に従って慎重に設定する必要があります。
1. 管理コンソールへのログイン
管理コンソールにログインします。この際、必ず安全な環境から管理者アカウントを使用してアクセスします。
また、多要素認証が利用可能な場合は、必ず有効化します。
2. ポート制御メニューへの移動
多くのファイアウォール製品では「セキュリティ設定」や「ポート管理」といったメニューにポート制御の設定項目が配置されています。
3. 許可するポートと遮断するポートの指定
HTTP(80番ポート)やHTTPS(443番ポート)など、必要最小限のポートのみを開放します。
特にリモートデスクトップ(3389番ポート)やSSH(22番ポート)といった管理用ポートは、慎重に管理すべきです。
また、未使用のポートは原則として、すべて閉じましょう。
4. 設定の保存と動作確認
設定変更後には必ず意図した通りにポート制御が機能しているかを確認します。
また、重要なサービスがブロックされていないかを確かめ、必要に応じて設定を調整します。
ネットワークアドレス変換(NAT)の設定方法
NATは外部から直接内部のIPアドレスが特定されるリスクを低減し、不正アクセスの防止に寄与する重要な技術です。
以下の手順で設定します。
1. NATルールの作成と優先順位の設定
内部IPアドレスと外部IPアドレスの対応関係を定義します。
静的NATが必要なサーバーは、個別にマッピングを設定します。
一方、動的NATを使用する場合は、変換に使用するIPアドレスプールを設定する必要があります。
その際、もっとも具体的なルールを上位に配置し、汎用的なルールは下位に配置します。
ルールの優先順位を確認し、意図しない動作の防止が重要です。
2. 動作検証とセキュリティポリシーとの整合性確認
NATルールがセキュリティポリシーと矛盾なく動作しているかを確認します。
ファイアウォールポリシーと整合性が取れているかを確認し、必要な通信が適切に許可されているかを検証します。
そのあと、内部ネットワークから外部ネットワークへの接続テストを実施し、ログを確認して想定通りにアドレス変換が行われているかを確認します。
問題が見つかった場合は、設定を修正します。
VPNの構築手順
リモートワークの普及に伴い、VPNの重要性は増しています。
VPNはファイアウォールと密接に連携し、安全なリモートアクセス環境を実現する重要な要素です。
ファイアウォールの設定と組み合わせることで、より強固なセキュリティを確保できます。
1. VPNプロトコルの選択と基本設定
まずは、利用用途に適したVPNプロトコルを選択します。
IPsecやSSL-VPNなどの選択肢があります。
ファイアウォールのVPNゲートウェイ機能を使用する場合、以下の設定が必要です。
- VPNトラフィックを許可するファイアウォールルールの作成
- VPN接続用の専用インターフェースの設定
- VPNトラフィックの暗号化設定(AES256など)
- 認証方式の設定(多要素認証推奨)
通信の安全性を確保するため、AES256など最新の推奨基準に基づいた暗号化アルゴリズムを設定します。
さらに、認証方式には可能な限り多要素認証を採用し、認証データが漏洩した場合でのリスク低減を図ります。
2. VPNプロファイルの作成
ユーザーごとのアクセス権限管理のため、VPNプロファイルを作成します。
これにユーザーグループごとのアクセス制限や、接続時間や同時接続数の制限を設定します。
また、IPアドレスプールを適切に配分します。
3. クライアント設定と動作テスト
VPN構築では適切なクライアントソフトウェアを選定し、接続設定情報を安全に配布します。
また、接続端末の安全性を高めるためにエンドポイントセキュリティ要件を定義し、適用します。
次に、スプリットトンネリングの設定を含めたセキュリティを設定して、必要に応じてトラフィックをVPN経由に限定します。
セッションが無駄に長引かないようにアイドルタイムアウトを設定し、ログ取得レベルを設定して、不正アクセスの兆候を監視します。
最後に動作テストを実施し、各ユーザーグループが正常に接続できるかを確認します。
加えてVPNの性能を測定し、必要に応じて設定を調整します。
セキュリティポリシーの実装
ファイアウォールにおけるセキュリティポリシーは、組織のセキュリティ要件を具体的なルールとして実装するものです。
これにより、不正アクセスの防止と適切なネットワークの利用が可能になります。
1. ホワイトリスト/ブラックリストの準備とルールの作成
まず、許可するトラフィックと拒否するトラフィックを明確に区別するため、ホワイトリストとブラックリストを作成します。
ホワイトリストには業務に必要な社内システムやクラウドサービスを含め、ブラックリストには既知の悪意あるIPアドレスや不要なアクセス元をリスト化します。
これに基づきトラフィックを制御するルールを設定します。
また、ホワイトリストに該当しないトラフィックは「拒否」するデフォルトポリシーを設定し、未定義のトラフィックの取り扱い方針を明確にします。
2. ルールの最適化
設定されたルールが複雑化すると管理が困難になるため、定期的に最適化をします。
重複するルールを統合して簡素化し、現在利用されていない未使用ルールを削除します。
より重要なルールを上位に配置して、ネットワークのパフォーマンスの向上を図ります。
3. 定期的なメンテナンス計画
最新の脅威や業務の変化に応じたリスト更新のため、定期的に見直しするスケジュールを設定します。
また、新規追加や削除をする際には、承認フローを設け、変更内容を記録して、監査へのスムーズな対応や運用管理の透明性を確保します。
さらに、ログや分析結果を活用して設定ルールの効果を測定し、必要に応じて調整します。
IPS/IDSの設定方法
IPS/IDSは、ファイアウォールのセキュリティ機能を補完し、より高度な脅威検知・防御を実現します。
ファイアウォールと統合することで、包括的なセキュリティ対策が可能になります。
1. 基本設定
IPS/IDSのセンサーは、ネットワーク内外の通信を監視できる位置に配置します。
また、IPS(防止モード)またはIDS(検知モード)のどちらを利用するかを選択し、ネットワークトラフィック量に応じたパフォーマンス設定を調整して、運用環境に適合させます。
また、ファイアウォールとIPS/IDSを連携させる際は、以下の点に注意が必要です。
- ファイアウォールのポリシーとIPS/IDSルールの整合性確保
- トラフィック検査の優先順位設定
- パフォーマンスへの影響を考慮した設定調整
2. 検知ルールとアラートの設定
次に、攻撃を検知するために必要なルールを設定します。
既存のシグネチャを有効化するだけでなく、特定のニーズに応じたカスタムルールの作成も可能です。
誤検知を防ぐため、検知ルールをチューニングして、運用負荷を最小限に抑えます。
また、アラートレベルを重要度に応じて通知方法を設定し、優先度の高い脅威やイベントはメール通知やSIEMツールとの連携により、担当者の迅速な対応につなげます。
3. レスポンスアクション設定
最後に、検知された脅威への対応を迅速化するためのレスポンスアクションを設定します。
自動で不正な通信をブロックするポリシーを適用し、インシデントレスポンス手順と連携して、被害拡大を防ぎます。
さらに、定期的に設定の見直しとテストをして、運用環境に適応した柔軟な対応ができる体制を構築します。
監視設定
効率的なログ管理のため、以下の項目を設定します。
ログローテーションの設定
ファイアウォールのログは、長期間保存するとストレージを圧迫するため、定期的なログローテーションが必要です。
たとえば「1か月ごと」や「ログ容量が1GBを超えたとき」などの条件でローテーションを実行する設定をします。
また、過去のログを保存する際は圧縮形式(例: ZIPやGZIP)でアーカイブすると、ストレージ消費を最小限に抑えられます。
重要なログはクラウドストレージやNASなどのバックアップ先に転送し、必要に応じて復元できる体制を整えます。
アラート閾値の設定
ファイアウォールの異常を早期に検出するには、適切なアラート閾値の設定が重要です。
たとえば、1分間に100回以上のログイン試行が発生した場合にアラートを発する設定や、トラフィック量が通常時の2倍を超えたときに通知を送信するルールを適用します。
アラートはメール、SMS、チャットやSIEMを介して担当者に通知され、エスカレーションルールに沿って対応します。
レポーティングの設定
定期的なレポートの自動生成は、セキュリティ状況を可視化するために有用です。
ファイアウォールの設定に基づき、週次や月次でトラフィック量、不正アクセスの試行回数、ブロックされた通信の数などを含むレポートをPDF形式で生成し、担当者やセキュリティチームに自動配信されるよう設定します。
ファイアウォールのセキュリティ保持における課題
ファイアウォールのセキュリティ強化には多岐にわたる設定が必要であり、専門知識を要する複雑な作業が求められます。
加えて、誤設定が引き起こすセキュリティリスクや管理負荷の増加なども考慮する必要があります。
特に中小企業において、これらの課題への対応は大きな負担となるケースが多くあります。
人的リソースの不足
ファイアウォールの運用には高度な専門知識が不可欠ですが、そのための人材確保が多くの企業にとって大きな課題となっています。
24時間365日体制の監視が望ましいものの、維持するには相当な人的リソースが必要なため、小規模なIT部門ではシフト制の監視体制の構築すら困難な場合があります。
また、セキュリティ担当者の育成には長期的な投資が必要であり、人材の定着率の問題も無視できません。
技術的な課題
セキュリティ脅威は絶え間なく進化しており、対応するための技術的なスキルや知識の更新が不可欠です。
特に注意が必要な技術的課題として以下が挙げられます。
- 新たなサイバー攻撃手法への対応
- クラウドサービスとの連携における設定の複雑化
- IoTデバイスの増加に伴うネットワーク境界の曖昧化
- リモートワークなど、社外や分散された環境のセキュリティ確保
さらに、ネットワーク構成の複雑化により、ファイアウォールの設定も高度化しています。
設定変更が必要な場面では、リスクを見極めつつ適切な対策を講じなければならず、些細なミスが脆弱性を生み出すおそれがあるため注意が必要です。
コスト面での課題
ファイアウォールを自社で導入・運用する場合、専門人材の育成や維持に多大なコストが発生します。
担当者の人件費やスキル向上のための教育費用だけでなく、継続的なセキュリティ強化に向けたハードウェアやソフトウェアの更新も欠かせません。
たとえば、最新のハードウェアファイアウォールを導入するには、初期費用として機器購入や設置費用がかかりますが、これにくわえて監視システムを構築するための追加コストがかかります。
導入後もソフトウェアのライセンス更新やセキュリティパッチの適用といった保守運用のコストも必要となるため、結果として、トータルコスト(TCO)が高くなりやすい傾向にあります。
自社運用vsマネージドサービス

マネージドファイアウォールサービスとは、ファイアウォールの構築から運用・保守までを専門のセキュリティベンダーが一括して提供するサービスです。
24時間365日の監視体制、最新の脅威インテリジェンスの活用、専門エンジニアによる迅速な対応が可能で、包括的なセキュリティ対策を提供します。
ファイアウォールの運用方式を検討する際は、自社での運用とマネージドサービスの活用、それぞれのメリット・デメリットを理解して、適切な選択をしましょう。
自社運用のメリット・デメリット
自社運用の最大の利点は、自社の要件やセキュリティポリシーに合わせた細かなカスタマイズができる点です。
たとえば、自社の運用方針に基づき柔軟に設定を変更し、機密情報を閉じた環境で管理できる点が強みです。
しかし、専門人材の確保や育成にかかるコストと労力は大きな負担です。
24時間365日の監視体制の維持は中小企業にとって難しく、技術革新への継続的な対応や投資も求められます。
すべての運用を自社で管理するため、すべてのリスクと責任を自社で負わなければならない点も、自社運用のデメリットといえます。
マネージドサービス活用のメリット
マネージドサービスを活用すると、専門チームによる24時間365日の監視体制が整い、最新のセキュリティ技術や脅威情報を活用できます。
これにより、インシデント発生時の迅速な対応やコンプライアンス要件への適合が容易になります。
また、運用コストを予算化しやすく、スケーラブルな対応が可能なので、ビジネスの成長に応じて柔軟な調整ができます。
特に、運用負荷を軽減し、自社のリソースを本業に集中させられる点は大きな利点です。
外部の専門業者によるサービスを活用すれば、自社で対応しにくい高度なセキュリティ対策ができ、効率的な運用が可能になります。
まとめ~運用体制を整えてファイアウォールを導入しよう~
ファイアウォールの効果的な導入や運用には、適切な設定と専門的な知識が求められます。
特にアクセス制御や監視体制、コンプライアンス対応を徹底することが重要ですが、すべて自社で賄うのが難しい場合は、24時間体制の監視や迅速な脅威対応が可能なマネージドサービスが有効な解決策となる場合があります。
マネージドファイアウォールサービスの利点と活用法を下記のホワイトペーパーで詳しく解説しています。ぜひ下記リンクからダウンロードしてみてください。
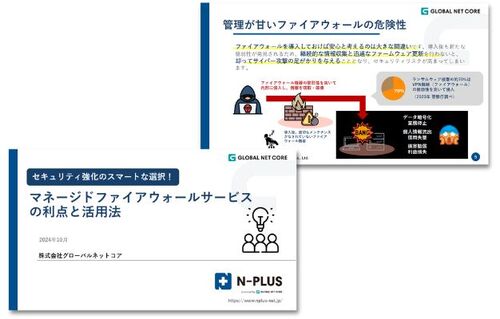
<ファイアウォールの導入を検討中の企業のみなさまへ>
次々と新しいサイバー攻撃の手口や情報漏洩などのニュースが話題になる中、今や、企業のセキュリティ対策はウイルスソフトだけでは難しくなっています。
そんな中で、どのようなセキュリティ対策を行うべきか、また、脅威への対策か十分かどうか不安を抱えていませんか?
社内ネットワークを守るファイアウォールの導入をご検討しているなら20年以上サーバーの構築・運用を手掛け、ネットワークのプロでもある当社にお任せください!
経験豊富な技術者が御社に最適なファイアウォール、セキュリティ対策をご提案します。



