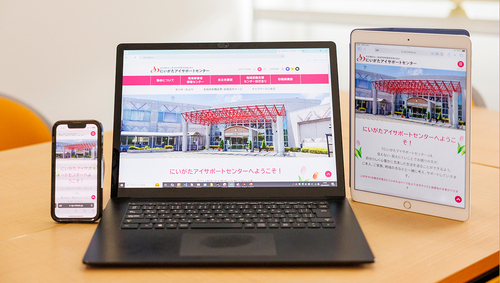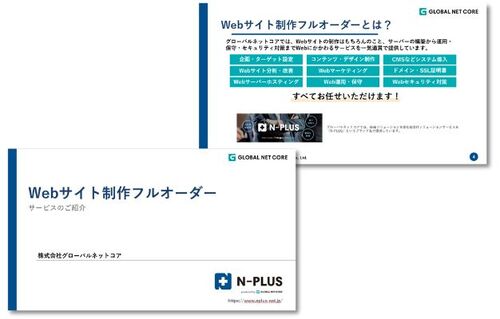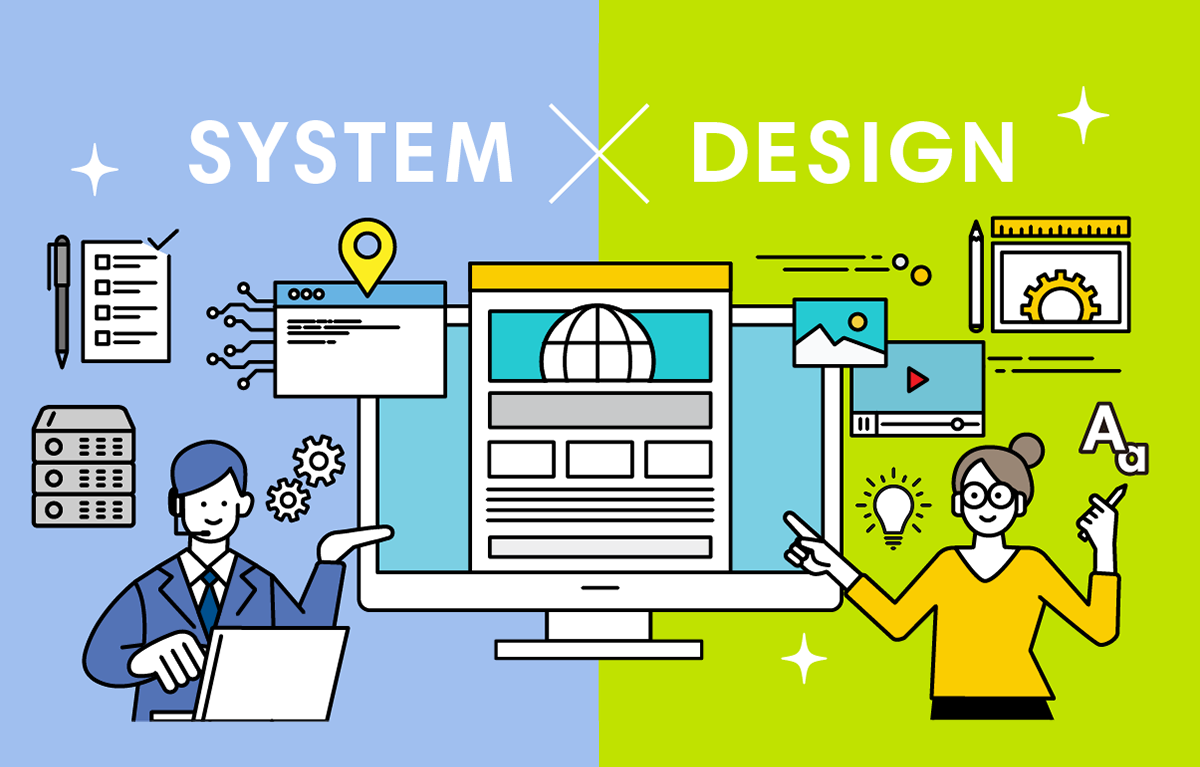ウェブアクセシビリティとは?考え方と規格、対応方法を解説!
2025.04.30(水)
- Webシステム

ウェブアクセシビリティの確保は、情報化社会において誰もが平等に情報にアクセスできる環境を実現するための重要な取り組みです。
2024年4月の法改正により、民間企業もウェブアクセシビリティに対応したWebサイトを整備することが努力義務化されました。
しかし、Webサイトでの具体的な実装方法や運用体制の構築に迷っている民間企業の担当者の方も多いのではないでしょうか。
ウェブアクセシビリティへの対応を怠ると、適切な情報提供が行えないだけでなく、企業価値やブランドイメージにも影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、ウェブアクセシビリティの考え方から具体的な対応手順、さらにはWebサイトへの実装におけるポイントまでを解説します。
より多くの人々が平等に利用できるWebサイトを実現するための指針として、ぜひ参考にしてみてください。
ウェブアクセシビリティとは?

ウェブアクセシビリティとは、現代社会において生活に不可欠な情報源であるWebサイトを誰もが平等に利用できることを指します。
デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」では、ユーザーの障害の有無や程度、年齢や利用環境にかかわらず、Webサイト上で提供されている情報やサービスを利用できること、またはその到達度を意味すると定義されています。
例えば、下記のような対応を行っている状態を「ウェブアクセシビリティが確保されている」と言います。
- 文字サイズの調整機能を実装する
- ページのタイトルや画像の代替テキストを適切に設定する
- キーボードでも操作できるナビゲーションにする
- サイト内の文章はなるべくわかりやすい言葉・表現を使う
2024年4月の障害者差別解消法の改正により、民間事業者にも障害がある方への合理的配慮※を提供することが義務付けられました。
これにより、障害がある方の障壁(バリア)を取り除くよう、環境の整備をすることが努力義務となりました。
「合理的配慮の義務化」に法的な罰則はありませんが、誰もが平等にWebサイトを利用するための「環境の整備」の一環として、ウェブアクセシビリティ対応は行うべきといえます。
日常生活の例では、「飲食店で車いすのまま着席できるスペースを作る」「窓口で筆談を用いて意思疎通する」などが合理的配慮にあたる。
参考:政府広報オンライン「ウェブアクセシビリティとは? 分かりやすくゼロから解説!」
ウェブアクセシビリティで恩恵を受けるユーザー
ウェブアクセシビリティは、さまざまなユーザーの利便性を向上させますが、特に該当するユーザーは以下のとおりです。
- 視覚障害のある方
- 聴覚障害のある方
- 上肢に障害のある方
- 高齢の方
- 色覚特性のある方
- 発達障害や学習障害のある方
- 一時的な障害を持つ方
(眼鏡をかけ忘れた方、手の怪我でマウスが思うように操作できない方 など)
ウェブアクセシビリティの重要性
現代社会において、Webサイトは重要な情報源で、社会生活を営む上でなくてはならない情報インフラのひとつになっています。
しかし、ウェブアクセシビリティに配慮して作られていないWebサイトでは、障害を持つ人が必要な情報を入手できなかったり、場合によってはWeb上で提供されているサービスを利用できなくなったりするなど、不利益が生じる可能性があります。
また、災害・緊急時にもWebサイトは重要な情報源となります。
ウェブアクセシビリティ対応の遅れにより、避難経路やライフライン情報など、命にかかわる重要な情報が思うように入手できないケースも想定されます。
Webサイトで提供している情報やサービスを誰もが安心して常に利用できるように、ウェブアクセシビリティへの対応は企業や団体が果たすべき社会的責任のひとつといえるでしょう。
アクセシビリティとユーザビリティの違い
アクセシビリティとユーザビリティは、Webサイトの品質を高める上で密接に関連する重要な指標ですが、目的には明確な違いが存在します。
アクセシビリティとユーザビリティの違いを以下の表でまとめました。
目的 |
詳細 |
|
アクセシビリティ |
障害を持つ人を含め、全ての人がウェブコンテンツにアクセスできるようにする |
すべての人が平等にWebサイトを操作し、情報を得られるようにするための技術を実装したり、デザインの工夫をしたりする |
ユーザリビティ |
Webサイトの操作性や分かりやすさを向上させる |
Webサイトの構造や導線の最適化を行い、直感的な操作性を実現する |
アクセシビリティとユーザビリティは相互に補完し合うものであり、両方を考慮することで、より広いユーザー層が快適に使いやすいWebサイトを実現できます。
ウェブアクセシビリティ対応による効果
ここでは、ウェブアクセシビリティ対応によって得られる効果について説明します。
より多くの人がWebサイトを活用できる
ウェブアクセシビリティを向上させることにより、Webサイトが高齢の方や障害のある方にとっても安心して利用できるようになります。
ウェブアクセシビリティを確保するための技術をWebサイトに実装することにより、より多くのユーザーにとっての利便性を高め、スムーズな情報収集を可能にします。
企業イメージの向上につながる
ウェブアクセシビリティへの積極的な取り組みを行うことは、企業イメージの向上にもつながります。
法律で努力義務化されたウェブアクセシビリティへの対応を進めることで、法律・法令遵守の意識が高い企業であるという印象を与えられるでしょう。
また、障害のある方や高齢の方など様々なユーザーに配慮することで、SDGs(持続可能な開発目標)やESG活動のための取り組みにつながります。
企業の総合的な価値向上を実現する重要な経営戦略としても、ウェブアクセシビリティ対応は必要といえます。
SEO対策にも効果がある
ウェブアクセシビリティの向上は、検索エンジン最適化(SEO)においても大きなメリットがあります。
Googleをはじめとする検索エンジンは、Webサイトの品質評価において、アクセシビリティを重要な判断基準として位置づけており、適切な対応はサイトの検索順位向上に直結します。
また、Webサイトが使いやすくなることにより、ユーザーの滞在時間を延長させることができ、直帰率の低下にも貢献します。
検索エンジンはユーザーの行動もWebサイトの評価指標としているため、結果としてウェブアクセシビリティの確保がWebサイト全体の検索パフォーマンス向上につながるといえます。
ウェブアクセシビリティの規格

ウェブアクセシビリティ対応にあたっては、指標とすべきガイドラインが制定されています。
ここでは、国際規格であるWCAGと日本向け規格のJIS X 8341-3について紹介します。
WCAG
WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、国際的なウェブアクセシビリティの標準化を目指すためのガイドラインです。
ウェブ技術の国際標準化を目指す組織であるW3C(World Wide Web Consortium)によって1999年に初めて策定され、2025年3月現在は「WCAG2.2」が最新バージョンとなっています。
WCAGは世界各国においてウェブアクセシビリティを定めるための基準になっており、後ほど詳しく解説するJIS X 8341-3のベースにもなっています。
JIS X 8341-3
JIS X 8341-3は、日本国内の企業や組織がウェブアクセシビリティを実現するための指標となる国家規格です。
日本工業標準調査会(JISC)が制定しており、WCAGにおけるウェブアクセシビリティの考え方を踏襲しつつ、日本の法制度に対応するための規格となっています。
2016年に改訂が行われたため、「JIS X 8341-3:2016」と表記されることもあります。
日本国内でウェブアクセシビリティ対応を進める際は、JIS X 8341-3に基づいて対応が進められるケースがほとんどです。
JIS X 8341-3のガイドライン
ここでは、日本国内におけるウェブアクセシビリティの実現と実務的な観点から、JIS X 8341-3の基本原則や適合レベル、対応状況を証明する方法を詳しく解説していきます。
JIS X 8341-3の基本原則
JIS X 8341-3は、ウェブアクセシビリティを確保している状態として「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」の4つの原則を示しています。
ここでは、基本原則の具体的な内容とそれぞれの対応例について解説します。
知覚可能
知覚可能は、ユーザーがWebサイトの情報や機能を認識できることを意味します。
視覚や聴覚に障害のある方でも、Webページに記載されている内容を理解できるようにする必要があります。
知覚可能に関する具体的な対応例は以下の通りです。
対応方法 |
説明 |
代替テキストの提供 |
画像やアイコンに適切な代替テキストを付与し、スクリーンリーダーで読み上げられるようにする。 |
動画への字幕追加 |
動画コンテンツに字幕を付けることで、聴覚に障害のある方も内容を理解できるようにする。 |
コントラスト比の確保 |
テキストと背景のコントラスト比を適切に設定し、目の見えにくい方や色覚異常の方にも読みやすいようにする。 |
操作可能
操作可能とは、ユーザーがWebサイトのインターフェースを問題なく操作できることを指します。
キーボードのみで操作ができるようにしたり、コンテンツの操作時間を確保したりすることが必要です。
操作可能に関する具体的な対応例は以下の通りです。
対応方法 |
説明 |
キーボード操作の保証 |
マウスを使用できない人のために、すべての機能をキーボードだけで操作できるようにする。 |
十分な操作時間の確保 |
時間制限のあるコンテンツでは、ユーザーが自分のペースで操作できるように時間を延長したり、制限を解除したりできるようにする。 |
ナビゲーションの簡素化 |
サイト内の移動を容易にするため、一貫性のあるナビゲーション構造を提供する。 |
理解可能
理解可能とは、ユーザーがWebサイトの情報や操作方法を容易に理解できることを意味します。
明確で一貫性のあるナビゲーションを設置することや、エラー発生時に分かりやすくメッセージを表示することなどが求められます。
理解可能に関する具体的な対応例は以下の通りです。
対応方法 |
説明 |
明確なラベル付け |
フォームの入力欄やボタンに明確なラベルを付け、ユーザーが何をすべきか理解しやすくする。 |
分かりやすいナビゲーション |
サイト全体で一貫したデザインやレイアウトを使用し、ユーザーが迷わずに操作できるようにする。 |
エラー時の適切なフィードバック |
フォーム入力時などのエラーを分かりやすい文章で表示し、修正方法を具体的に示す。 |
堅牢
堅牢とは、Webサイトが様々な環境や技術で正しく機能することを指します。
ユーザーごとに異なる閲覧環境や支援技術との互換性を確保することが重要です。
堅牢に関する具体的な対応例は以下の通りです。
対応方法 |
説明 |
標準的なHTML/CSSの使用 |
W3Cの標準に準拠したHTML/CSSを使用し、様々なブラウザや支援技術との互換性を確保する。 |
レスポンシブデザインの採用 |
様々な画面サイズやデバイスに対応できるレスポンシブデザインを採用する。 |
JIS X 8341-3の適合レベル
JIS X 8341-3の達成基準は、適合レベルA/AA/AAAの3段階に分けられており、各レベルごとに達成していなければならない基準が決まっています。
ここでは、適合レベルごとに主要な達成基準とその対応例を詳しく解説します。
レベルA
適合レベルAは、基本的なウェブアクセシビリティ要件を満たすための25の達成基準で構成されています。
このレベルの対応基準を満たすことで、最低限のアクセシビリティを確保することができます。
適合レベルAのおもな達成基準と対応例は下記の通りです。
基準 |
対応 |
1.1.1 |
画像や動画・音声など、テキスト以外で提供されるウェブコンテンツを設置する際は、代替テキストを設定してコンテンツの内容が伝わるようにする。 |
1.4.1 |
色覚異常のある人や目の見えにくい人、高齢の人など色を識別しづらい人でも見やすい色の組み合わせにしたり、テキストで補助情報を掲載したりする。 |
1.4.2 |
音声や動画は自動再生せず、ユーザーの操作で停止・非表示できる機能を実装する。 |
2.4.2 |
Webサイト内の各ページには、ページ内容が端的に分かるタイトルをつける。 |
適合レベルAA
適合レベルAAは国際的なウェブアクセシビリティ対応を行うための13の達成基準で構成されています。
日本国内では、総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」によって、国及び地方公共団体等の公的機関が運用するWebサイトはJIS X 8341-3:2016の適合レベルAAへの対応を速やかに進めなければならないとされています。
なお、適合レベルAAへの対応を目指す場合は、適合レベルAの25の達成基準も必ずクリアしている必要があるので注意しましょう。
適合レベルAAのおもな達成基準と対応例は以下の通りです。
基準 |
対応 |
1.4.3 |
目の見えにくい人がウェブコンテンツ内のテキストを読めるように、テキストと背景色のコントラストを十分に確保する。 |
1.4.4 |
目の見えにくい人が画面拡大ソフトなどを使わずにウェブコンテンツ内のテキストをそのまま読むことができるようにする。 |
2.4.5 |
ユーザーが自分に合った手段によってWebサイト内のページを見つけられるように、検索機能やページ内のリンクなど複数の方法を用意する。 |
3.2.3 |
Webサイト内に設置されるナビゲーションは一貫した表示・レイアウトにする。 |
適合レベルAAA
適合レベルAAAは、適合レベルA、AAよりもさらに発展的なウェブアクセシビリティの準拠を目指すための23項目の基準で構成されています。
コンテンツの中には適合レベルAAAの達成基準をすべて満たすことができないものもあるため、積極的に準拠をめざすことは推奨されていません。
デジタル庁の「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」では、まずは適合レベルAAに準拠することを目標にし、可能であれば適合レベルAAAの達成基準を数個追加して試験することが望ましいとされています。
目指すべき適合レベルは?
官公庁・自治体のWebサイトでは、先述の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」によってJIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに対応しなければならないとされています。
民間企業のWebサイトにおいて明確なガイドラインは存在していませんが、適合レベルAAへの対応を目指すことがひとつの目安となるでしょう。
また、JIS X 8341-3の理解と普及を促進しているウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)が「JIS X 8341-3:2016 達成基準 早見表(レベルA & AA)」を公開しています。
各レベルの達成基準を確認しつつ、自社のWebサイトに求められるアクセシビリティを検討しましょう。
JIS X 8341-3への対応を証明する方法は?
JIS X 8341-3はJISマーク表示制度の対象規格ではないため、対応状況がひと目で分かりづらい状態となっています。
JIS X 8341-3への対応状況をユーザーに示すためには、「供給者適合宣言」もしくは、WAICの「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」に基づく方法があります。
供給者適合宣言
Webサイトの供給者もしくは第三者がウェブアクセシビリティ対応状況について試験を行い、JIS X 8341-3への対応度合いと試験結果を表明する方法です。
供給者適合宣言は、以下のJIS規格に基づいて作成する必要があります。
- JIS Q 17050-1:2005 適合性評価−供給者適合宣言−第1部:一般要求事項
- JIS Q 17050-2:2005 適合性評価−供給者適合宣言−第2部:支援文書
ですが、試験範囲が膨大になったり、宣言書の作成に手間やコストがかかったりと、実際には対応が難しい場合があります。
「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」
WAICによって定められたガイドラインに基づいて、JIS X 8341-3への対応度合いを表明する方法です。
このガイドラインに則ると、Webサイトの対応度を「準拠」「一部準拠」「配慮」という3段階で示すことができます。
「準拠」とは、アクセシビリティ試験の結果、目標の適合レベルに該当する達成基準をすべて満たしている状態を指します。
「一部準拠」はアクセシビリティ試験の結果、目標の適合レベルに該当する達成基準をすべて満たしていない場合、今後の対応方針を示すことで表記することができます。
「配慮」は、試験の実施有無や結果によらず、WebサイトがJIS X 8341-3に基づいて制作されており、ウェブアクセシビリティ確保のための取り組みを行っていることを示します。
準拠/一部準拠/配慮の違いと、それぞれの基準を満たすために必要な対応を表にまとめました。
対応度 |
ウェブアクセシビリティ方針の |
試験の実施 |
試験結果の公開 |
準拠 |
必要 |
必要 |
必要 |
一部準拠 |
必要 |
必要 |
任意 |
配慮 |
必要 |
不要 |
不要 |
対応度を「準拠」とする場合は、アクセシビリティ試験の実施と試験結果の公開が必須となりますので注意しましょう。
ウェブアクセシビリティ対応の進め方

JIS X 8341-3を基準としたウェブアクセシビリティ対応のために必要なステップを解説していきます。
必要な手順を整理し、漏れのないように進めていきましょう。
1.適合レベルと対応の度合いを決める
ウェブアクセシビリティ対応の一歩目は、自社のWebサイトにおける目標の設定を行うことです。
目標とする適合レベルと対応度合いを明確に定めることで、具体的な実装計画が可能となり、効率的にアクセシビリティ対応を進めることができます。
前章で解説した「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」に沿って目標を決定すると、アクセシビリティ試験への対応や方針の作成がスムーズになります。
自社の状況やWebサイトの役割やターゲットとなるユーザーに応じて、適合レベルと対応度を決定しましょう。
2.ウェブアクセシビリティ方針を策定する
ウェブアクセシビリティ方針は、組織としてのアクセシビリティへの取り組み姿勢を明確に示す文書です。
WAICの「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」では、ウェブアクセシビリティ方針の提示または公開が必須となっていますので、忘れずに策定しなければなりません。
WAICが定めている「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」に、詳しいウェブアクセシビリティ方針の策定方法がありますので、それに基づいて作成しましょう。
ウェブアクセシビリティ方針の策定では、まず対象範囲を明確に定義する必要があります。
Webサイト全体を対象とするのか、特定のページや機能に限定するのかを具体的に示しましょう。
また、目標とする適合レベルと対応度も記載します。
例えば「対象範囲となっているWebページは、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠」といった形で、明確に文章化しましょう。
未対応の部分がある場合は、その理由と今後の対応方針についても言及することで、継続的にアクセシビリティを確保・改善する姿勢をユーザーに示すことができます。
3.設計と試験を行う
目指す適合レベル・対応度が決まったら、Webサイト上で改修が必要な箇所の洗い出しと設計を行います。
Webサイトの制作を外部業者に委託している場合は、業者ともすり合わせを行いながら進めていきましょう。
特に新規開発や大規模なリニューアルの際には、企画段階からウェブアクセシビリティへの対応を考慮することで、後からの改修コストを大幅に削減できます。
ウェブアクセシビリティ試験では、総務省が提供する「みんなのアクセシビリティ評価ツール:miChecker」などの自動チェックツールを使うこともできます。
しかし、自動チェックツールによる試験だけでは不十分であり、実際のユーザー体験を考慮した検証や、目視によるチェックも行う必要があります。
WAICの「JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン」を活用することで、より詳細な検証が行うことができます。
4.試験結果をWebサイトで公開する
試験結果を踏まえ、1.で定めた適合レベル・対応度合いに合致しているかを確認して公表します。
ウェブアクセシビリティへの「準拠」を表明する場合は、試験結果の公開が必須となっていますので注意してください。
試験結果の公開にあたっては、以下の情報を明確に記載しましょう。
- 対象となるウェブページの情報、URL
- 目標としているJIS X 8341-3の適合レベル
- 試験方法
- 試験結果
- 今後の改善計画
試験結果の公表は、ユーザーにWebサイトがJIS X 8341-3に適合しているという説明責任を果たすとともに、継続的なアクセシビリティ改善への姿勢を示すものとなります。
試験結果の公表が任意となっている「一部準拠」の場合でも、未対応部分と改善計画を含めて公表することをおすすめします。
定期的に試験を行い、改修を続けることでより幅広いユーザーにとって使いやすいWebサイトを実現することができるでしょう。
まとめ~積極的にウェブアクセシビリティ対応を進めよう~
ウェブアクセシビリティについては、2024年4月の障害者差別解消法の改正により、民間企業のWebサイトでもこれまで以上に積極的な対応が求められるようになりました。
ウェブアクセシビリティを向上させるための取り組みは、誰にとっても分かりやすい・操作しやすいWebサイトを実現できるだけでなく、企業のイメージ向上にもつながります。
デジタル庁やWAICのガイドラインを参考にしながら、自社サイトで取り入れられるウェブアクセシビリティ対応と、継続的な改善を進めていきましょう。
ウェブアクセシビリティ対応でお悩みの企業ご担当者様へ
「ウェブアクセシビリティ対応の進め方が分からない」「具体的な対応方法に迷っている」など、ウェブアクセシビリティ対応に関するお悩みはございませんか?
グローバルネットコアでは、ユーザビリティ・アクセシビリティに配慮した分かりやすいWebサイトの制作を強みとしています。
また、JIS X 8341-3:2016等級A/AAに準拠したWebサイトのコーディングや、Webサイト運用におけるアクセシビリティ対応のためのご提案・支援も行います。
まずは、貴社のウェブアクセシビリティに関する課題について、お気軽にお聞かせください。